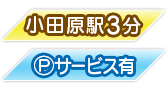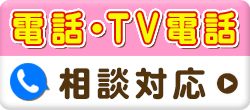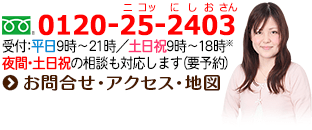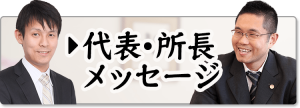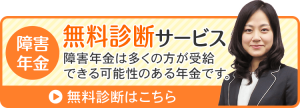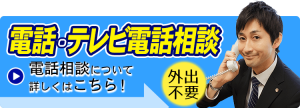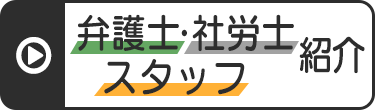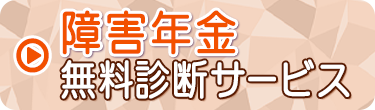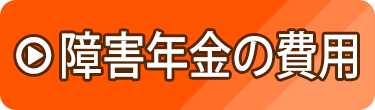障害年金を受給することのリスクはあるのか
1 障害年金を受給することによるリスク 2 傷病手当金を受給する場合に障害年金受給の事実を勤務先に知られる可能性がある 3 社会保険の扶養から外れる可能性がある 4 国民年金保険料の法定免除を利用した場合に老齢基礎年金の受給額が減る 5 死亡一時金や寡婦年金をもらえなくなる 6 障害年金については私たちにご相談ください。
1 障害年金を受給することによるリスク
障害年金の制度の目的は、障害によりお金を稼ぐことが難しくなった人の収入を補うことですが、その一方で、障害年金の受給の事実を知られたり、障害年金の受給等により他の制度からの給付に影響を及ぼすことがあります。
以下、そのようなリスクについてご説明いたします。
2 傷病手当金を受給する場合に障害年金受給の事実を勤務先に知られる可能性がある
障害年金を受給してもその受給の事実を第三者に知られることは通常ありません。
しかし、傷病手当金の申請書類には、今回傷病手当金を申請するのと同一の傷病で障害厚生年金または障害手当金を受給しているか否かを回答させる問いが設けられています。
そのため、傷病手当金の申請をする場合には、勤務先に障害年金受給の事実を知られる可能性があります。
3 社会保険の扶養から外れる可能性がある
社会保険の被扶養者の範囲について、障害年金の受給者である場合には年間収入が180万円未満であることが要件の一つとされています。
したがって、障害年金の年金額が180万円以上になる場合や、障害年金と他の収入を合わせて年間180万円以上になる場合には、社会保険の被扶養者から外れます。
この場合、ご自身で国民健康保険に加入して保険料を負担し、国民年金の1号被保険者として国民年金保険料を負担する必要があります。
4 国民年金保険料の法定免除を利用した場合に老齢基礎年金の受給額が減る
障害年金の等級が2級以上の場合、申請手続きにより、国民年金保険料の納付を全額免除してもらうことができます(これを「法定免除」といいます。)。
法定免除の適用を受けると、障害年金の受給権を取得した日が属する月の前月分から保険料の納付が免除されます。
ただし、法定免除を受けると、その期間については老齢基礎年金の受給額に反映される金額が2分の1として計算されます。
したがって、将来、障害の程度が軽くなって障害年金を受給することができなくなり、老齢基礎年金を受給することになる場合には影響を及ぼします。
なお、法定免除された保険料については10年以内に追納が可能とされています。
5 死亡一時金や寡婦年金をもらえなくなる
⑴ 死亡一時金について
死亡一時金とは、死亡日の前日において国民年金の1号被保険者として保険料を納めた月数および国民年金の保険料免除期間が36か月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなったとき、その方と生計を同じくしていた遺族が受けることができるものです。
したがって、2級以上の障害年金を受給する場合には上記要件を満たさなくなるため、死亡一時金をもらえなくなります。
⑵ 寡婦年金について
寡婦年金とは、死亡日の前日において国民年金の1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されるものです。
なお、亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません(令和3年3月31日以前の死亡の場合、亡くなった夫が障害基礎年金の受給権者であったときも支給されません)。
したがって、2級以上の障害年金として現に受給した場合(令和3年3月31日以前の死亡の場合は受給権者だった場合も含む)には、寡婦年金をもらえなくなります。
6 障害年金については私たちにご相談ください。
私たちは、数多くの障害年金の事案を取り扱っております。
障害年金を受給することでどのような影響があるかご相談されたい場合には、お気軽にご連絡ください。